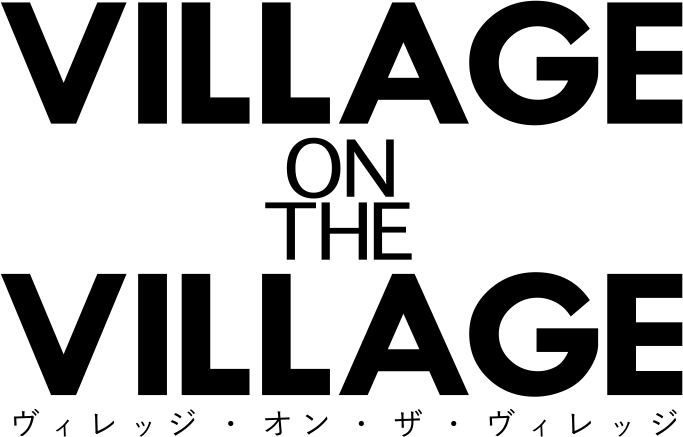鈴木卓爾さん(古賀) ロング・インタビュー

- Q:映画に参加しようと思った理由は?
-
鈴木卓爾:映画美学校の喫煙スペースがまだあった頃に、黒川さんから声を掛けられて初めて知り合い、脚本を渡されました。その頃は滅茶苦茶忙しくてどうしようかなとも思ったんですけど、僕自身が普通のセリフに飽きていたところがあって、本作の脚本のセリフに興味を持ちました。
『ジョギング渡り鳥』は映画美学校のアクターズコースの生徒さんたちとエチュードで作ったんですが、そこで自分はエチュードのセリフにずっとこだわりを持っていたなと振り返って気づくことがありました。自分の中で映画のセリフは嘘くさいということが、観念としてはずっと現在進行形であったんですね。それで『ジョギング〜』では、「作られたセリフのようなもの」を現場で言っていくという日常化の作業をしながら、やがてちょっと自動化に到るみたいな、そういう方法を新たに模索してみようと思って。でも、長い間そうして自分で映画を作ってる間に、時たま外に出て来てみると、また事情が変わっていたり感触が変わってたりする。
『Village On The Village』のセリフは、エチュードではなく書かれたセリフだし、非常にフィクショナルなものなんだけれど、ただそのセリフの意味するものは何もなかったりして、意味からはすごく自由だと思いました。片岡義男さんみたいなセリフの言い回しでありながら、描かれている世界は、そういうシティポップとか言われていた70年代から80年代のバブル期の消費を促進するための言葉遣いの商業目的のトレンディーなドラマみたいなものからは遠ざかっていて。ある意味陰惨な世界じゃないですか、すごく悲惨なのに誰も悲惨に思わないという。言葉にしてしまわないようにしているものに向かうためのプロセスとして上品だなという感触があって、片岡義男じゃなくても、音楽で言ったらシティポップの松本隆とかああいう人たちが本来持っていたであろう、純粋に言葉とか音楽とかアメリカのポップスからもらって、日本人なりに咀嚼して語っていくという元々のエッセンスと似た感触で(自分でセリフとして)「言えそうだぞ」みたいな、その脚本に対する興味がとても強かったです。
それが大きな理由だったのと、もう一つはのっぽのグーニーの田中淳一郎くんの出演が決まっていたことです。脚本はcore of bellsの山形さんが担当だったり、日常で音楽として楽しんでいたミュージシャンが参加していたことに惹かれました。作品は観てなかったのですが、鎮西尚一監督の『ring my bell』という映画にcore of bellsのメンバーが出演していたということは知っていたので。そういう人たちが集まって一つの映画が作られるのだとしたらぜひ参加したいなと思いました。そこは最初の頃の黒沢清監督の『ドレミファ娘の血は騒ぐ』のような、そういうニューウェーブ以降の、少し後の映画の反応みたいなところに本作を通じてタイムスリップできるなという感じがありました。そういうところはいままで自分でくぐり抜けて来ていないので、参加したいという意識が強いというか、思い切って芝居ができるんじゃないかと思いました。僕の中での根拠はたくさんあったんですよ。お金持ちになった後の矢沢永吉であるとか。そういうのをやってみたいという気持ちがすごくあってやりました。
- Q:出演する決定打というものはありましたか?
- 卓爾:田中淳一郎くんの出演がやっぱり大きいかなと思います。音楽をやってる人がいるって、ギスギスした映画を作る進行の焦りとかそういったものと無縁に現場に関われる予感があって。忙しいんだけど、日程だけ空けちゃえば、多分そこに没入できるだろうなという期待感があったんです。それは的中していましたよね。宮崎駿さんが見に来たりだとか、東小金井は行ったことがなかったので切り離されていたし、出演者はみなすごくよかったなと思います。
- Q:皆が集まると映画の雰囲気に近い、ちょっとしたユートピアみたいでしたね。
- 卓爾:うん、宮崎晋太朗さんとか本当にいいなあ、うまいなあと思ったり、すごく楽でしたね。素直に芝居ができるというか…黒川さん自身はすごく映画をたくさん見てるし、いろんなこと考えているんだけど、現場に生じてることを信じてくださるんで、NGみたいなことの境界線が窮屈に設定されてないような気がしたし、だから僕は現場でイライラしてなかったですよね?ぜんぜん。
- Q:はい、ムードを作る中心になってくださってた。
- 卓爾:いえいえ。だから好き勝手やらせていただいたなという感じが強くあったりして。やっぱり行ってよかったなと。インド富士も食べれたり。いいことばっかりでした(笑)だから、完成もとっても楽しみだったし、この間観た試写で思った以上の…なんていうか、映画は跳ねるっていうかその思想っていうのはあるっていうか、その間違いのなさみたいなのも本当にうまくいっているなっていう感じがあったんですね。
- Q:脚本を読んだときと、完成してみて、何か違いはありましたか?
-
卓爾:脚本読んだときタイトルも違ってたんですけど、『(LOSS TIME before) magical night falls』という言葉がすごくかっこよくて、ただそれは青臭いといえば青臭いタイトルなので変更になっちゃったのかもしれないのですが、なんか勝手に僕が醸造していたエモーションなイメージみたいなのは、完成した映画にはあまりなかった。僕ちょっと「ツイン・ピークス」みたいなイメージがあったんですけど、そういうエモーショナルなもの、アンジェロ・バダラメンティの音楽とか、そういう感じは全くなくって、もっともっとキレキレのビートで打ってく感じのなかに、脚本のときよりずっとこう…人の映ってる映画になってるって感じがあるのがとってもよくて、お客さんが好きになってくれたり、リピートして見に来てくれたりしそうな映画だなと思います。本当に黒川さんてすごいなと思うんですよ。もっと監督させたくなりますね。
ただ、こういう映画誰が見るのかみたいな映画ではあると思うんですけど、本当に、それは『ジョギング渡り鳥』のときもそうなんだけれども、愛される映画になって欲しいなと思います。
- Q:この映画で好きなところ、やってて一番楽しくてそれがうまく出ているところなどありますか?
-
卓爾:なんか本当に夕方遊び場に遊びに行って、おもちゃとかいろんなものをその場に置いてきて、ほったらかして、翌日また遊びに来てっていう、子どもたちが三輪車砂場に置いてくみたいな、ああいう感じでぽこぽこと百草園のあたりの遊び場みたいなロケ地が記憶に残ってて、スズメバチの巣があったりして、お借りしたおうちの庭に黄色い花が咲いてたりとかして、あの花を大切にしたいなと思ったりして。
場面でいうと、酔いつぶれて横になってるときに女がドアをドンドン叩いて襲ってくるところで、あそこのいい加減さとかってすごい好きですね。
カメラマンも素晴らしいですよね。いろんな好きなところあるんだけど、長宗我部さんが演じた小野寺先輩のシーン、あれはどこで撮ってるかわからないけどあそこら辺の光の印象がとてもよかったり、また長さんが全く歳をとっていないという(笑)、人魚の肉を食べてしまったようなそんな感じがして。
何かいろんな物語を喚起するという作りになっているというか、そういった仕掛けに満ちているなと思いました。
-
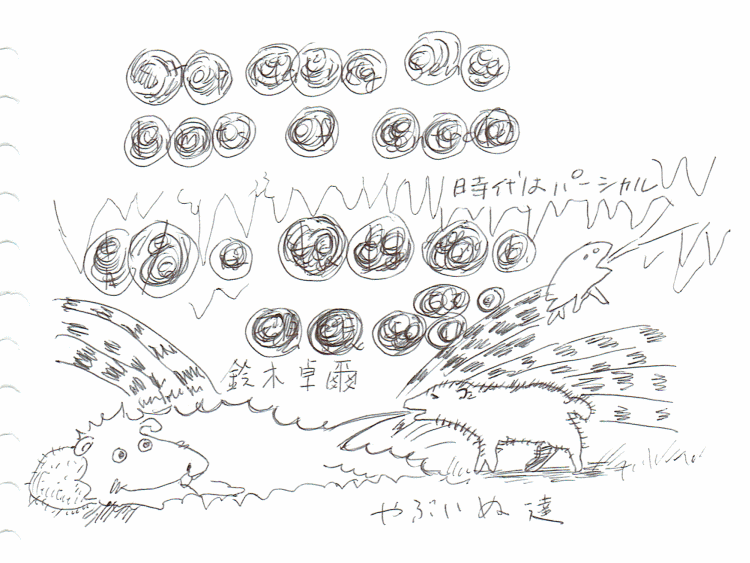
- Q:卓爾さんは、俳優やってるときと監督として現場にいるときって全くモードは切り替わるんですか?
-
卓爾:嫌なんだけど、切り替わっちゃうことが多いですね。監督やってるほうが責任も重くて。本当は自分が監督するときにベストコンディションなのは、まるで俳優のように回路が全部開くっていう感じのときで。俳優やってるときはその開くまでが難しいなって思っていたりして、監督やってるときのほうが自由だろうなって思いながら、監督のときはそういうモードになるには制約が大きいのでなかなかなれないっていう矛盾を抱えていて。監督の第一目的と俳優の第一目的は違いがあるんですが、俳優は間違いないようにしゃべんなきゃとか、ちゃんと準備していかないとまずいぞとか、そういうことを乗り越えたうえでだと、結構乗れるんですけど。乗れるっていってもやっぱり役のなかでだと思うので、結構制約は抱えた上でやっていて。ただ『Village On The Village』は本当に贅沢でした。
映画監督って、人によっては計画したものがその通りに撮られていく楽しさみたいなこととか、逆に計画したものがその通りに段取られていくことにつまんないという感触を現場で思ったりとか、そういう様なものだと思うんですけど。これでいいんだろうかのオンパレードですよ、監督やってるときって。俳優はもう監督が悩んでるもんだから、こっちも悩む必要ないなっていう感じで、僕なんかどんな言い間違いがあっても、もう一回っていう気にならない。もっとうまく出来る自信もないので。
- Q:どっち側の気持ちもわかっちゃう良さと、窮屈さみたいなのがあったりします?
- 卓爾:でも、『Village On The Village』をどう撮るかとか、そんな段取りのことは全く現場では考えたりはしてなかったつもりなんです。なんか演出してたかもしれないですけど。
- Q:実際助かってたみたいですよ。悩んだりするとアイディア出してくれたりして。
- 卓爾:えっ全然覚えてないんだけど。どうしようかって言われたこともあったかもしれない。そこで気負わないでそうしてくれる監督がいてくれてホント助かるっていうか、どうしたらいい?って言ってくれたら。ただ、正しいかどうかはすごく自信がない。俳優はどうしても肉体的な記憶しかないんで、肉体的なリサーチと行動とやっぱりその根拠を記憶にして次動く根拠にしていくっていうことしかないので。たまにそれをブツ切りにしてあるポジションポジションでしか想定してない監督さんっているので、こっちは全部繋げて考えてやらないと動けない。俳優の側が結構調整して、ホントはここをこう経由してここに来ないといけないとわかったうえで、こっからここに行ったフリをするっていう風に忙しく俳優が対応してたりすることがあるんですけども。今回はそんなことはなくて。お芝居に関しては、あらかじめ編集された何かを監督が現場で見ちゃってる様な目を見ると、ちょっと絶望するんですけど。それは今やんないで欲しいみたいなことって、でもそれ普通にあるんですよ。「そんなのはいらないんだよ」っていわれると殴りたくなるっていうか(笑)。そこにそういう歪んだ権力志向、どうしようもない格差が生まれていってしまうんですが、(『Village On The Village』には)そういうものはないですよねぇ、間違いはないっていうか。まぁ柴田さんも相当自由だし。どこまで真面目なのか、考えてるのかわかんないけど。「からあげ食べてきちゃった~」とか言って。
- Q:さっきのお話聞いて思ったのは、柴田さんもおそらくイメージ的にはエモーショナルな部分がある仕上がりをイメージしてたんじゃないかなっていう気がして。
- 卓爾:あぁそうだよね。ストーリーの展開はやっぱり俳優やってて頼りにしちゃうから、そんときのこう他人をハグした時の温かみとかいうことを、頼りにすることでやってたりするけど、結果にそれが現れなくても全然オッケーっていうか、やれればいいわけでって感じでやってるかな。だから、うん、あのテレビ電話で話したところとかもいいキャスティングの人があそこに現れたり。よくまぁホントにボランティアの人も含めてみんな楽しそうにしてましたよね。
黒川さんには今度メロドラマ撮って欲しいですね。ダグラス・サーク的な - Q:あー、すごい悲惨な話を
- 卓爾:笑 監督の換骨奪胎性ていうのは、今後もどうなるんだろうかなあ